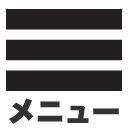試合規定
2025年1月20日
① 連盟規定
原則として、本年度の『公認野球規則』および『全日本軟式野球連盟の競技者必携』に定める規則を準用する。以下、練馬区学童野球連盟の規定とする。
② 競技運営に関する注意事項
- (1)出場資格について
- 原則として、練馬区に在住又は在学(いずれも、過去に在籍の場合も可とする)する児童とする。
チームの編成、登録は男女を問わない。
連盟大会の出場資格は、3年生以上とする。
(新人戦大会、4年生大会、ジュニア交流大会の出場資格は、各大会で定める)
※出場選手は、スポーツ保険に加入していること。 - (2)出場選手登録表の取り扱いについて
- 連盟HPより所定の用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえデータにて提出する。
連盟印(角印朱)を押印し1部をチームに返却される。
※開会式以降の登録は認めない。 - (3)出場選手登録数について
- 10名以上、25名以下とする。
- (4)背番号について
- 選手は0番から99番まで(主将は10番)とし、監督は30番、コーチは29番、28番及び27番(代理コーチ)、26番(代理コーチ)とする。
但し、4年生以下の大会についてはコーチと重複しない限り、20番以上でも可能とする。 - (5)ベンチ入れる人数について
- 最大4名までとし、監督1名・コーチ2名・スコアラー1名とする。
代理監督は原則としてコーチ2名のうちのいずれかとし背番号は元のままとする(30番は付けない)。但し、打順表の監督欄に"代理" を記入し、その旨を本部に申し出ること。
また、コーチの代理も認める。熱中症対策として、保護者2名以内をベンチに入れる事ができる。 - (6)スコアラーについて
- ユニフォームや審判服の着用は認めない。アマチュアスポーツ・学童野球に相応しいスポーティーな
服装とし、所属チームの帽子を必ず着帽すること。また、必ずスコアブックを付けること。
(コーチがスコアラーを兼任する場合はユニフォームで行うこと)。 - (7)チームの集合について
- 試合開始予定時刻の30分前とし、速やかに大会本部に打順表を提出すること。
打順表は、ボールペンを使用し直筆1枚(本部用)、複写3枚(球審、対戦チーム及び自チーム用)計4枚を本部に提出すること。※この時点で、ジャンケンにて先攻・後攻を決める。 - (8)ベンチについて
- 抽選番号の若い番号のチームが一塁側とする。(決勝戦は先攻3塁側、後攻1塁側とする)
- (9)打順表について
- 打順表の照合は原則として本部記録員が行う。
登録表と照合の結果、誤記に気づいた場合
◆試合開始前の場合、注意を与えて書き直し(訂正)させる。
◆試合中に判明した場合、判明した時点で正しく改めさせる。
※氏名、背番号の誤記、登録選手間の背番号のつけ間違いは、判明時点で修正、罰則適用なし。
※登録外選手が判明①(出場前):出場を差し止め、ベンチから退去させる。罰則適用なし。
※登録外選手が判明②(出場後):試合中なら没収試合、試合後なら勝利の取り消し。
打順表へは登録表に記載された監督及び選手を全員フルネームで記入すること。 - (10)ブルペンにおける"投手のウォーミングアップ"の取り決めについて
- 次試合の先発投手のみウォーミングアップを認める。捕手は、原則としてベンチ入り指導者。
また、ヘルメットを着用した補助の選手を立たせ、打球に注意させること。
打順表を提出し照合を受けた後、4回終了または1時間10分を経過した後、ブルペンの使用を認める(5回戦試合は3回終了または45分を経過した後)。 - (11)その他注意事項
- ヘルメット着用:打者、次打者、走者、ベースコーチ、ボールボーイはヘルメットを着用すること。
選手交代:監督がタイムをかけ、球審に申し出ること。
抗議のできる者:監督か当該プレーヤーとする。
ベンチ内での電子機器使用:電子スコア記録用として1台の使用を認める。
指示用メガホン:ベンチ内に限り1個の使用を認める。
移動車両:制限台数を順守のこと。各車両にはプロント面のわかりやすい場所にチーム名を提示。
試合終了後のグランド整備:両チームが協力して行う。
③ 特別規則
- (1) 人数について
- 試合開始時および終了時に9名以上いないチームは棄権とみなす。
- (2) 試合時間について
- 大会は6回戦または時間制限として試合開始後1時間30分を経過した場合は新しいイニングに入らない(5回戦の場合は1時間15分)。
正式試合は5回を終了で成立するが、5回以前にも規定時間に達したならばゲームは成立する。
(5回戦の場合は4回終了で成立するが、4回以前にも規定時間に達したならばゲームは成立する) - (3) コールドゲームについて
- 得点差によるコールドゲームは
A:3回終了15点差、4回終了10点差、5回以降7点差
とする。
B:3回終了10点差、4回終了7点差 - (4) シートノックについて
- シートノックは決勝戦以外行わない。ただし大会運営上行わない場合もある。
ノッカーは選手と同様のユニフォームを着用し、捕手はレガース、プロテクター、SGマークのついた捕手用ヘルメット及びファウルカップを着用しなければならない。 - (5) 給水タイムについて
- 守備時間が長い場合、健康維持を考慮し、審判員の判断で給水を設ける(試合時間には入れない)。
- (6) タイブレークについて
- 延長戦は行わず、6回終了または制限時間を過ぎて同点の場合は、タイブレーク方式を行う。無死1、2塁、継続打順で最大2イニングまで行い、同点の場合は抽選で勝敗を決める。
- (7) 特別継続試合について
- 暗黒降雨などで、5回以前に中止となった場合でも特別継続試合とする。
- (8) 投手の投球制限について
- 1人1日、5・6年生は70球以内、4年生以下は60球以内(以下カッコ内)とする。
ダブルヘッダーの場合でも1投手1日70球(60球)以内とする。
試合中に70球(60球)に達した場合は、その打者が打撃を完了するか、攻守交代まで投球できる。
ボークにもかかわらず投球したものは、投球数に含める。
タイブレークになった場合は、1日70球(60球)以内であれば引き続き投球する事ができる。 - (9) 臨時代走について
- 打者が頭部にヒットバイピッチを受けた場合、または塁上の走者が負傷した場合で、一時走者を代えないと試合中断が長引くと審判員が判断した時は臨時代走の措置を行う事ができる。
但し試合に出場中に選手に限られ、投手と捕手を除いた選手のうち直前に打撃終了した選手とする。 - (10)投手の守備位置交代について
- 特に制限をしない。
例)投手-野手-野手-投手
例)投手-野手-投手-野手 - (11)サングラスの使用について
- 大会本部の承認なしに使用できる。ただし投手はミラーレンズサングラスの使用はできない。
また野手がサングラスを帽子の庇(ひさし)の上にのせることを認める。 - (12)DHの採用
- 野球規則書5.11指名打者(a)のみ採用とし、(b)は採用しない。
- (13)ハイコンバットの使用について
- 使用可否は会場ルールに準じて対応する。
・光が丘第7小跡地グラウンドは禁止とするが(ウレタンバット、スポンジバット、ビヨンドなど)、FRPは可とする。
④ 禁止事項、試合のスピードアップ、マナーアップに関する注意事項
- (1)審判員の判断に基づく制裁に対し、異議を唱えることは許されない。
- (2)投手が投球動作を開始したら投手の動揺を誘うような声を発してはならない。
- (3)ボール回しは禁止とする。
- (4)試合中、スパイクの紐を意図的に結びなおすためのタイムは認めない。
- (5)監督はタイムを要求するとき以外は、みだりにベンチを出てはならない。
- (6)攻守交代はかけ足でスピーディに行うこと。監督が投手のもとへ行き来する場合も小走りで行うこと。
- (7)投球を受けた捕手は、その場から速やかに投手に返球すること。
- (8)投手が捕手のサインを見るときは、必ず投手板について見ること。
- (9)捕手から返球を受けた投手は、速やかに投手板に触れて投球姿勢をとること。
- (10)打者は速やかにバッターボックスに入ること。またサインはバッターボックス内で見ること。
- (11)次打者は必ず次打者席で立って待つこと(素振りは禁止)。
- (12)試合時の応援等については、投手が投球動作に入った時点で止めること。また、選手の動揺を誘うような言動は行なわないこと。
⑤ 用具、装備具に関する注意事項
- (1)バットは、公認野球規則で規定されるもののほか、次による。
-
- ・木製バットは公認制度を適用しない。ただし着色の制限はある。
- ・金属、ハイコンバットはJ.S.B.Bのマークをつけた全軟連公認のものに限る。
- ・後付グリップ等、全軟連公認のバットに付足しや改造が見受けられた場合は使用を禁止する。
- (2)捕手は、J.S.B.Bのマークをつけた全軟連公認のレガース、プロテクターおよびSGマーク付きのマスク
- (スロートガード付)、捕手用ヘルメット、ファウルカップを着用しなければならない。
- (3)打者、次打者、走者、ベースコーチはJ.S.B.Bのマークをつけた全軟連公認およびSGマーク付きで
- 両側にイヤーフラップのついたヘルメットを着用しなければならない。
- (4)ユニフォーム、スパイク等は、次に定めるものを着用しなければならない。
-
- ・同一チームの監督、コーチ、選手は同色、同形、同意匠のユニフォームでなければならない。
- ・アンダーシャツは全員同色のものでなければならない。
- ・帽子は全員同色、同形、同意匠のもの、またストッキングは全員同色のものでなければならない。
- ・スパイクの色は自由とし、全員同色でなくても構わない。金属製金具のついたスパイクは使用できない。
- ・ネックウォーマーは季節を考慮し着用できる。
- ・守備時における手袋の使用は投手を除き認める。
- ・投手が走者となった場合のジャンパーの着用は、天候等を考慮し審判員が認めた場合のみ許可する。一塁・三塁のベースコーチも同様とする。但し、原則としてチームの統一ジャンパーとする。